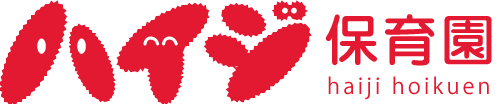2025年3月「卒園おめでとう!」
3月15日土曜日に卒園式が無事に終わりました。今年の年長さんは、みーちゃん(在園年数3年半)しょう君(4年9ヶ月)はや君(5年)こうちゃん(5年7ヶ月)と本当に小さいときからハイジにきてくれていました。
今年も卒園児のももちゃんママの2人で作ったDVDを流しました。
小さかった頃から6才になるまでの写真や動画が映し出されます。楽しかった日、悔しかった日、大騒ぎした日、大泣きした日、大笑いした日、全身泥だらけになって遊んだ日…
見ている子どもも大人も「うっわ~!」と叫んだり…笑ったり…
一気に過去を振り返って(あの頃大変だった~。そうだった。大変だった~。)と見ている感慨深い時間になってくれたようです。今年もDVDが無事に作れて一安心!よかったー!
ハイジを始めたとき『子ども一人一人が本当の姿が出せ、いっぱい喜んだりいっぱい怒ったりたまには哀しいこともあって、でもいろいろあるけど楽しい!』と思える保育園を作りたいと思って始めました。子どもが喜怒哀楽を出してありのままの姿で過ごせる場所です。
ありのままを出せる場所…ってことはがんばったり無理したりはしない。本当の自分をさらけ出せる場所ってことにもなります。それは自分が主体的に動ける場所でもあります。でもそれは楽で楽しくて何のストレスもないのか??ってことではないとも思っていて…
自分が主体的に動くことによって、ケンカになることもあるし嫌われることもあるし一人になることもある。自分がどうしたいか?を自分で決めるしかない場所。しかも自分で決めたことなので自分に返ってくる。人のせいにはできないってことでもある。
全然楽しくない日もあれば、めっちゃ楽しい日もある。
ハイジに入園してからずっと、友だちができるか?どうして嫌われたか?どうやったら許してもらえるか?どうやったら自分の遊びにみんながついてきてくれるか?などを毎日自分で考えて動いていた子どもたちがここを卒園してある程度決まったルールがある学校にいくということは、今までのようには主体的に動けないだろうし…
学校のルールに合わせる。先生の言うことを聞く。友だちに合わせる。そんな時間が増えていくということでもあります。
きっと…今…日本中の年長さんと親御さんたちの中には「学校大丈夫かなぁ~?」「友だちできるかなぁ~?」「保育園辞めたくないなぁ~?」「このままがいい~!」って思っている人がたーくさんいるんだろうなぁ~とも思っています。
これは通っていた保育園や幼稚園が楽しければ楽しいほど、別れがつらければつらいほど、主体的に動くことができていればいるほど、通っていた保育園や幼稚園を卒園して学校に入学するということは親も子どももハードルが高いってことにもなるんだろうなぁ~とも思っています。
ハードルが高いことで学校に入学することへの不安に押しつぶされそうになるくらいならハードルを下げることもありかも?なんて考えてみることもあります。例えばハイジでもルールを増やしたり、大人と子どもの関係は対等ではなく(子どもと対等に意見は言い合えているつもりです)大人が上で子どもが下という関係になり大人が決めたことを子どもにはしっかりやってもらう…など…
う~ん。でもそれはないかなぁ~。というかそれはムリだなぁ~。
私は迷ったとき悩んだときにいつもこの本のこの部分を思いだします。
【ほんとのことは親にはいえない 著者 木村泰子 ドキュメンタリー映画「みんなの学校」大空小学校初代校長】
一部を書いてみますね。
“東日本大震災のあった2011年3月11日。
宮城県石巻市の釜谷地区にあった大川小学校。当時、学校にいた78人のうち、74人の子どもが命を失いました。奇跡的に4人だけが生き残りましたが、あとは全員先生の指示に従って命を失ってしまいました。
あの大きな長い地震のあと、子どもたちは運動場で校長からの「避難指示」を待っていました。でも、指示が届かない。50分以上経ってから、先生たちがこれ以上待てないとなり、避難訓練通りに行動しようということに決めました。避難先は、小学校の近くにある北上川の堤防近くの三角地帯と呼ばれる道路でした。
全員で歩き始めたそのときには、もう津波が北上川の堤防を突破しようとしていたんです。すごい音が鳴り響いていた。子どもの何人かが、「あっちにいったら怖い。山へ逃げよう」と道を引き返して、学校の裏山の方向に慌てて走り出したんです。
そのときに、「勝手なことをしてはいけない。言うことをきいてついてきなさい」と先生に連れ戻された子どもたちは、津波に命を奪われた。
たった4人だけが生き残った。その子たちは、自分だけが生き残ったというとてつもない苦しい時期を経て大人になって、一人の子は今、「語り部」の活動を始めています。
岩手県釜石市の釜石東中学校と鵜住居小学校では、「なにかあったら、先生の指示を待たず、自分から山へ逃げて命を守りなさい」と、日常からくり返していたんですね。津波がくる前に、中学生が小学生の子どもの手を引いて、学校へ来ていた子は全員が山に登り、命が助かりました。同じような沿岸地域の教育現場です。
こうした事実から、私たち大人は、真摯に問い直しをしないといけない。命が亡くなるって、とり返しがつかないことじゃないですか。くり返したらあかん。
私はいつも考えます。自分がそのときその場にいる教員なら、同じことをしていた可能性は山ほどある、と。
この話をする目的は批判ではありません。事実として受け止めて、やっぱり問い直しを続けないといけない。子どもを守れなかったのは、同じ日本社会に生きる私たち大人全員でもあると。そのことを言葉では伝えきれないほど感じているからです。”
出典:木村泰子(2021年)『「ほんとのこと」は、親にはいえない 子どもの言葉を生み出す対話』家の光協会
私はこの本を読んだ数年後に大川小学校に行き、語り部(津波で当時高校生だった息子さんを亡くしたという女性の方でした)の方と裏山に登って話を聞いてきました。語り部さんはとても元気な方でした。「風化されないように語り継ぐ」と話していたので思い切ってハイジだよりにも書いています。
私はこの本を歯医者さんの待合室で読んだ時からずーっとずーっと「子どもの主体性を大切にしなくちゃいけない。」と思って過ごしています。
ハイジで12月くらいに少し大きな地震がありました。全員で部屋の真ん中に集まろうとしていた時、みーちゃん(6才)が当時まだハイハイしていたこて君(1才)をさっと抱っこして大人の近くに連れてきてくれました。みーちゃんに「どうして?連れてきてくれたの?」と聞いたら「だって。こて君は歩けないから」の返事。
すぐに木村先生の本を思い出しました。みーちゃんは自分で考えて行動する。ってことができる人になっているんだなぁ~と安心したりもして…
本当にうれしかったです。
卒園児のみんなへ
これからはありのままの姿で過ごすことは難しいかもしれない。でも何がしたいか?何がしたくないか?自分の気持ちだけは大切にできる人になってくれていると思う。
この先大人になるまでも長い時間がかかるけど…大人になってからも、もーっともーっと長い人生になります。みんなの根っこの部分には(自分を大切にする)ということを植え付けることはできたんじゃないかなぁ~と思っているのでこの先何があったとしても、自分で選べることができて、きっと何かしらの壁にぶつかったとしても何とか乗り切っていける力も身についている!というか身についてくれていたらいいなぁ~と思っています。
きっと大丈夫!
卒園!おめでとう!
卒園児のパパママへ
ハイジを選んでくれたこと本当に感謝しています。
これからだって大変なことも沢山あるかもしれないけどきっと大丈夫!
私たち大人だって子どもたちに負けないくらい楽しい人生を送りましょうね~
本当にありがとうございました。
これからも末永くよろしくお願いします。
2025年3月25日